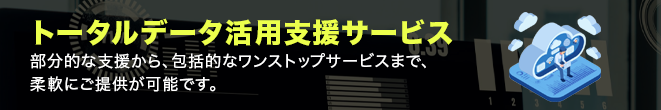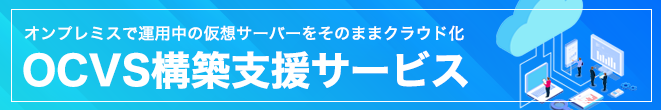生成AIの活用事例13選!生成AIの導入時のポイントや注意点なども解説。

ChatGPTの登場により、生成AIは単なる話題の技術から、企業の競争力を左右する重要なツールへと進化しました。国内企業の約8割が生成AIの活用を始めている今、導入に踏み切れない企業は取り残されるリスクに直面しています。
本記事では、実際に生成AIを導入して大きな成果を上げた国内企業13社の事例を詳しく紹介します。さらに、導入を成功させるための実践的なポイントと、事前に知っておくべきリスクについても解説していきます。
目次
- 1 なぜ今、企業は生成AIに注目しているのか
- 2 業界別にみる生成AI活用の最前線13事例
- 2.1 【製造業】パナソニックが実現した年間18万時間の削減効果
- 2.2 【食品】江崎グリコが問い合わせ対応を3割削減した秘訣
- 2.3 【飲料】コカ・コーラが仕掛けた消費者参加型マーケティング
- 2.4 【教育】ベネッセが1万5千人の社員に展開したAI活用術
- 2.5 【物流】ヤマト運輸が挑む配送予測の精度向上
- 2.6 【小売】セブン-イレブンが発注時間を半減させた方法
- 2.7 【IT】noteがクリック率を2割向上させたパーソナライズ戦略
- 2.8 【建設】大林組が目指す設計期間の大幅短縮
- 2.9 【金融】SMBCが開発した「2秒に1回使われる」AIツール
- 2.10 【金融】みずほ銀行が稟議書作成を10分に短縮した仕組み
- 2.11 【通信】KDDIがプログラミング時間を8割削減した研修プログラム
- 2.12 【自治体】別府市が2週間の業務を2日で完了させた改革
- 2.13 【EC】メルカリが実現した「誰でも簡単出品」の裏側
- 3 生成AI導入を成功に導く6つの実践ポイント
- 4 導入前に知っておくべき4つのリスクと対策
- 5 生成AI活用で変わる未来の働き方
なぜ今、企業は生成AIに注目しているのか
人手不足と業務効率化への切実なニーズが、企業を生成AI活用へと駆り立てています。単純作業の自動化だけでなく、創造的な業務支援まで可能になった生成AIは、もはや「あれば便利」から「なければ困る」存在へと変わりつつあります。
業界別にみる生成AI活用の最前線13事例
【製造業】パナソニックが実現した年間18万時間の削減効果
パナソニックコネクトは、全社員向けのAIアシスタント「ConnectAI」を導入し、驚異的な成果を収めました。
同社では「耐薬品性のある樹脂材料を探したい」といった専門的な質問から、事業アイデアの創出まで幅広く活用。導入から1年で年間約18万6000時間の労働時間削減を達成し、16カ月間で情報漏洩などの問題も発生していません。
大企業でありながら他社の事例を待たず、失敗を恐れない企業文化が早期導入を可能にしました。
出典:パナソニック「パナソニック コネクト 生成AI導入1年の実績と今後の活用構想」
【食品】江崎グリコが問い合わせ対応を3割削減した秘訣
創業100年を超える江崎グリコは、AIチャットボットの導入により社内外の問い合わせ対応を劇的に改善しました。
複数の社内ポータルに散在していた情報を一元化し、社員が必要な情報を素早く検索できる仕組みを構築。その結果、バックオフィス部門への問い合わせが約30%減少し、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
需要予測や商品開発期間の短縮にも生成AIを活用し、全社的な変革を進めています。
出典:Allganize Japan「■導入事例■【Glicoグループ様】30%の社内問い合わせ対応を削減。顕在化したバックオフィスの課題を「Alli」で解決」
【飲料】コカ・コーラが仕掛けた消費者参加型マーケティング
日本コカ・コーラは、画像生成AI「Create Real Magic」を活用した画期的なキャンペーンを展開しました。
消費者が自由にボトルデザインやロゴを作成できるプラットフォームを公開。優秀作品は実際の屋外広告やSNSで採用され、ブランドと消費者の新しい関係性を構築することに成功しました。
単なる広告ではなく、消費者を巻き込んだ体験型マーケティングとして、業界に新たな可能性を示しています。
出典:AIsmiley編集部「コカ・コーラ、「Create Real Magic」公開。AI画像生成で自分だけのクリスマスカード制作が可能に」
【教育】ベネッセが1万5千人の社員に展開したAI活用術
ベネッセホールディングスは、グループ全体の生産性向上を目指し、独自開発の「Benesse GPT」を1万5000人の社員に提供しています。
イントラネット上で社内情報を効率的に検索・要約できる仕組みを構築。コーポレート部門では、AIが業務分析を行い改善点を提示することで、人的リソース不足の解消に成功しました。
セキュリティに配慮した設計により、機密情報を扱う業務でも安心して活用できる環境を実現しています。
出典:Benesse公式ブログ「社内AIチャット「Benesse GPT」をグループ社員1.5万人に向けに提供開始」
【物流】ヤマト運輸が挑む配送予測の精度向上
ヤマト運輸は、全国約6500拠点の荷物量を予測する「荷物量予測システム」を開発し、物流の最適化に成功しました。
地域差や季節変動が大きい配送業務において、3~4カ月先の荷物量を高精度で予測。従業員のシフト作成や車両配置の最適化により、人手不足問題への対応と業務効率化を同時に実現しました。
MLOpsの導入により予測精度の継続的な改善も可能となり、業界全体のモデルケースとなっています。
出典:エクサウィザーズ「ヤマト運輸、MLOpsで経営リソースの最適配置を実現」
【小売】セブン-イレブンが発注時間を半減させた方法
セブン-イレブン・ジャパンは、全店舗にAI発注システムを導入し、店舗運営の大幅な効率化を達成しました。
過去の販売実績と天候データを分析し、最適な発注数をAIが自動提案。発注作業時間を約4割削減することで、スタッフは接客や教育により多くの時間を割けるようになりました。
品切れ防止と在庫の適正化も実現し、顧客満足度の向上にもつながっています。
出典:セブンイレブン「店内作業効率化の取り組み」
【IT】noteがクリック率を2割向上させたパーソナライズ戦略
note株式会社は、AWSの機械学習技術を活用してコンテンツ配信を最適化しました。
ユーザーの閲覧履歴や関心事を分析し、一人ひとりに最適なコンテンツを表示する仕組みを構築。その結果、クリック率(CTR)が20%向上し、ユーザーエンゲージメントの大幅な改善を実現しました。
配信速度の向上と運用コストの削減も同時に達成し、ビジネス成長を加速させています。
出典:AWS「Amazon Titan Text Embeddings の埋め込み表現で、レコメンド機能やタグ付けを実装」
【建設】大林組が目指す設計期間の大幅短縮
大林組は、建物の外観デザインを自動生成するAIシステムを開発し、設計プロセスの革新に挑戦しています。
過去の建築データと顧客要望を学習したAIが、多様なデザイン案を短時間で生成。従来数カ月かかっていた初期検討期間を1週間程度に短縮することを目標としています。
設計者はより創造的な業務に集中でき、顧客への提案スピードも大幅に向上する見込みです。
出典:JPXマネ部!「大林組がAIツール「AiCorb」で描く“建築設計の未来”」
【金融】SMBCが開発した「2秒に1回使われる」AIツール
SMBCグループは、Azure OpenAI Serviceを活用した社内専用AIアシスタント「SMBC-GAI」を開発しました。
専門用語の検索からメール作成、プログラミングまで幅広い業務をサポート。導入後、利用頻度は「2秒に1回」という驚異的な数字を記録し、全社的な生産性向上に大きく貢献しています。
情報漏洩を防ぐ専用環境での運用により、金融機関に求められる高いセキュリティ水準もクリアしています。
出典:SMBC「SMBCグループが独自に生み出したAIアシスタント「SMBC-GAI」開発秘話」
【金融】みずほ銀行が稟議書作成を10分に短縮した仕組み
みずほ銀行は、営業担当者の負担軽減を目的に、稟議書の自動作成システムを開発しました。
面談記録や財務データを入力すると、過去の稟議書や法令を学習したAIが適切な形式でドラフトを生成。従来1~2時間かかっていた作成時間を約10分に短縮し、最大92%の業務効率化を見込んでいます。
営業担当者は顧客対応により多くの時間を割けるようになり、サービス品質の向上にもつながっています。
出典:みずほフィナンシャルグループ「〈みずほ〉が見据える、10年後の金融。
生成AIを活用して、業務効率化と新たなイノベーションの実現へ。」
【通信】KDDIがプログラミング時間を8割削減した研修プログラム
KDDIは、社内版ChatGPT「KDDI AI-Chat」を1万人の社員に展開し、全社的なAI活用を推進しています。
特筆すべきは、全社員対象のプロンプトエンジニアリング研修を実施した点。その結果、従来1日かかっていたプログラミング作業が2~3時間で完了するなど、劇的な効率化を実現しました。
アンケート分析の効率化など、技術部門以外でも幅広い成果が報告されています。
出典:KDDI「社員1万人が「KDDI AI-Chat」の利用を開始」
【自治体】別府市が2週間の業務を2日で完了させた改革
別府市は、生成AIとRPAを組み合わせることで、行政業務の大幅な効率化を達成しました。
市民アンケートの自由記述欄をAIが自動分類し、従来2週間かかっていた分析作業を2日程度に短縮。手作業をほぼゼロにすることで、職員はより市民サービスに注力できるようになりました。
人手不足に悩む多くの自治体にとって、参考となる先進事例です。
出典:別府市デジタルファースト推進室 公式note「市民向け生成AIを活用したチャットボットサービスの実証運用【BEPPU×AI vol.4】」
【EC】メルカリが実現した「誰でも簡単出品」の裏側
メルカリは、2024年9月から「AI出品サポート」機能を提供開始しました。
写真をアップロードしてカテゴリーを選ぶだけで、商品タイトルや説明文を自動生成。「出品が面倒」という最大の課題を解決し、初心者でも最短3タップで出品を完了できるようになりました。
ユーザビリティの向上により、プラットフォーム全体の活性化につながっています。
出典:メルカリ「メルカリ、「AI出品サポート」の提供を開始。出品体験をさらに簡単にアップデート」
生成AI導入を成功に導く6つの実践ポイント
導入を検討する企業が増える中、成功と失敗を分けるポイントが明確になってきました。ここでは、先行企業の経験から導き出された6つの重要なポイントを解説します。
まずは業務の棚卸しから始める
生成AI導入の第一歩は、現状の業務プロセスを可視化することです。
どの業務に時間がかかっているか、どこにボトルネックがあるかを明確にすることで、AIを活用すべき領域が見えてきます。「とりあえず導入」ではなく、解決したい課題を特定してから動き出すことが重要です。
業務の優先順位をつけ、効果が見込めるところから段階的に導入することで、確実な成果につなげられます。
目的に合ったツール選びの重要性
生成AIツールは、テキスト生成、画像生成、音声生成など、それぞれ得意分野が異なります。
自社の目的に最適なツールを選ぶことが成功の鍵となります。無料版やトライアルを活用して実際の業務での使い勝手を確認し、効果を検証してから本格導入に移行することで、投資リスクを最小限に抑えられます。
複数のツールを比較検討し、費用対効果を慎重に見極めることが大切です。
社員教育なくして成功なし
どんなに優れたツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。
プロンプトの書き方から活用事例の共有まで、体系的な研修プログラムを用意することが不可欠です。KDDIのように全社員向けの研修を実施することで、組織全体のAIリテラシーを底上げし、自発的な活用を促進できます。
成功事例を社内で共有する仕組みも、活用促進には効果的です。
ルール作りで守るべき境界線
生成AIの活用には明確なルールが必要です。
「機密情報は入力しない」「生成物は必ず人間がチェックする」など、基本的なルールを定めることで、リスクを回避しながら安全に活用できます。また、誤った情報が生成された場合の対処フローも事前に決めておくことが重要です。
ルールは定期的に見直し、現場の実態に合わせて更新していく柔軟性も求められます。
セキュリティと利便性の両立方法
企業での生成AI活用において、セキュリティは最重要課題の一つです。
Azure OpenAI Serviceのような閉域環境で運用できるサービスを選択することで、機密情報を守りながら生成AIの恩恵を受けられます。アクセス権限の管理やログの監視など、技術面と運用面の両方から対策を講じることが必要です。
利便性を損なわない範囲でセキュリティを確保する、バランスの取れた設計が求められます。
小さく始めて大きく育てる導入戦略
いきなり全社展開するのではなく、特定の部署や業務から始めることが賢明です。
小規模な導入で効果を検証し、成功体験を積み重ねながら徐々に展開範囲を広げていく。このアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、組織に最適な活用方法を見つけられます。
PDCAサイクルを回しながら、継続的な改善を行うことが長期的な成功につながります。
導入前に知っておくべき4つのリスクと対策
生成AIは強力なツールである一方、適切に管理しなければ思わぬリスクを招く可能性があります。事前にリスクを理解し、対策を講じることで、安全な活用が可能になります。
情報漏洩リスクから会社を守る方法
生成AIに入力した情報が外部に漏れる可能性は、最も警戒すべきリスクです。
対策として、社外秘データの入力を禁止するルールを設け、必要に応じてデータをマスキング処理してから使用します。また、企業向けの閉域環境サービスを選択することで、情報漏洩リスクを大幅に低減できます。
定期的な監査とルールの周知徹底により、組織全体でリスク管理意識を高めることが重要です。
AIの「嘘」を見抜くためのチェック体制
生成AIが事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」への対策は必須です。
AIの出力を鵜呑みにせず、必ず人間が事実確認を行う体制を整えます。特に数値データや固有名詞については、信頼できる情報源と照合することが大切です。RAG技術を活用して社内の信頼できるデータベースと連携させることも有効な対策となります。
チェック項目をリスト化し、確認漏れを防ぐ仕組みづくりも効果的です。
著作権トラブルを避けるための基礎知識
生成AIが作成したコンテンツが既存の著作物に類似している場合、法的リスクが発生します。
対外的に公開する生成物については、必ず権利関係のチェックを行います。利用する生成AIサービスの利用規約を確認し、著作権の扱いについて理解しておくことも重要です。
疑わしい場合は公開を控え、オリジナリティを重視した活用を心がけることが賢明です。
倫理的な問題を防ぐ仕組みづくり
AIが差別的または偏見のある内容を生成するリスクも無視できません。
プロンプトに「差別的な内容は生成しない」といった指示を含めることで、ある程度の抑制は可能です。しかし、完全に防ぐことは難しいため、公開前の人間によるチェックは欠かせません。
企業として社会的責任を果たすため、倫理ガイドラインを策定し、全社員で共有することが求められます。
生成AI活用で変わる未来の働き方
ここまで紹介した13社の事例から分かるように、生成AIは業種や規模を問わず、確実に成果を生み出すツールとして定着しつつあります。重要なのは、自社の課題を明確にし、適切なツールを選んで段階的に導入していくことです。
リスクを理解し適切に対策を講じれば、生成AIは業務効率化の強力な味方となります。まずは生成AIを小規模に試してみる、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。
解析人材育成
収集
CC-BizMate
勤怠管理クラウドサービスCC-BizMateは出退勤管理・勤怠管理・労務管理・工数管理・プロジェクト管理・在宅勤務・テレワーク勤務など「人事総務部門に寄り添う」サービスです!
CC-Smart
CC-Smartは、カラ予約の防止、議事録の録音、きめ細やかな通知機能など「会議のムダ」 「会議室のムダ」を省くことで生産性向上をサポートする会議予約システムです。
WebNESTEE STAMP
WebNESTEE STAMPは、書式にこだわらない出社せずにハンコ付き書類が作れるサービスです。事前に書式を準備する必要がなく、Excel、PDF、画像データを指定経路に回覧し、承認ができます。手続きや承認に時間や余計な手間をかけず、本来の仕事に集中できます。
groWiz
MS PowerPlatformサービスを用いたgroWizスタートアップ、アイデアサポート、オーダーメイド、テクニカルサポート等、ニーズに合わせたご提案をいたします。
OCVS構築支援サービス
クラウド環境向けに大幅な設計変更をすることなくクラウドリフトを実現し、Oracle Cloud Infrastructure上でこれまでと同じ操作方法のまま VMware 製品のツールを利用することができます。オンプレミスで運用しているVMwareの仮想サーバーをそのままOracle Cloud環境へ移行することも可能です。
活用・分析
CC-Dash AI
CC-Dashは、AI技術を活用したコンサルティングサービスとPoCサービスをご提供しています。
お客様のビジネス課題を解決するために、専門の技術チームがヒアリングからPoCまでの一連のプロセスをサポートいたします。
小売業向け CC-Dash AI
数多くのデータに数理的な処理を用いることで、将来の需要量、在庫量の予測が可能です。
小売業にAIを導入することにより、労働者不足問題の解消、属人化の防止、適正な在庫管理などに役立てられます。
Data Knowledge
Data Knowledgeは、30年に渡り使用されている国産のBIツールです。多彩な分析レポートで「経営の見える化」を促進し、分析ノウハウ共有機能で全社の分析レベルをアップ。データ・リテラシーの向上につながります。
BIスターターパック
by Tableau / by Oracle Analytics Cloud
Tableau は、クラウドベースの分析プラットフォームです。誰とでもデータからの発見を共有することができます。同僚やお客様を Tableau Cloud に招待し、インタラクティブなビジュアライゼーションと正確なデータを共有すれば、潜んでいるチャンスを探し出すこともできます。
ADB移行支援サービス
Oracle Autonomous Database(ADB)とはオラクル社の提供している高性能かつ運用負荷を限りなく軽減する自律型のデータベース・クラウド・サービスです。移行をすることで、利用時間に応じた課金体系で優れたコスト・パフォーマンスを実現します。
保守
CC-Dashの保守サービス
BI導入後、ツールを最大限に活用することをサポートします。約25年の実績で安心と信頼の“保守サービス”。
お客様のビジネス状況に応じたQA対応~システム運用まで幅広くトータルサポートを提供し、社内のエンジニアの稼働時間を年間330時間削減!
BIサポート定額オプションサービス
せっかくBIツールを導入してもうまく活用できない。そんな方のためにユーザー利用状況分析レポート、システムヘルスチェックレポートなどを通して、安定したシステム活用を目指すサービスです