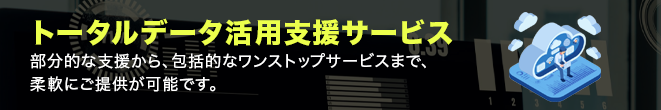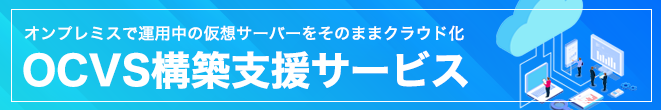DX認定制度とは?制度の概要や取得のメリット・申請方法などを一挙に解説

企業のデジタル変革が叫ばれる中、国が正式に認定する「DX認定制度」をご存知でしょうか。申請費用は完全無料でありながら、取得すれば低利融資や補助金の優遇、企業ブランド力の向上など多くのメリットが得られる制度です。本記事では、DX認定制度の概要から申請方法、取得後のメリットまで、企業経営者や担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。
目次
DX認定制度とは?国が認める企業変革の第一歩
DX認定制度は、経済産業省が2020年に創設した公的認定制度です。企業のデジタル変革への準備状況を国が認定することで、日本全体のDX推進を加速させることを目的としています。認定取得は企業規模や業種を問わず可能で、申請や維持に費用は一切かかりません。
経済産業省が認める「DX-Ready」企業の証明
DX認定制度は、正式には「情報処理の促進に関する法律第二十八条」に基づく認定制度です。経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」の基準を満たす企業を、DX推進の準備が整った状態、つまり「DX-Ready」な企業として認定します。
認定された企業は「DX認定事業者」と呼ばれ、国から正式なお墨付きを得たことになります。認定企業数は年々増加傾向にあり、特に中小企業での取得が急増しています。前年比で約1.4倍、中小企業に限れば約1.6倍という伸び率を示しており、制度の認知度と活用度が着実に高まっていることがわかります。最新の認定事業者一覧はIPAのサイトで公開されており、CSVファイルでダウンロードも可能です。
認定を受けた企業には専用のロゴマークが付与され、名刺や企業サイト、会社案内などに掲載することができます。このロゴは、企業がデジタル時代に適応し変革していく意志を持つことを対外的に示す重要なツールとなっています。
「2025年の崖」を乗り越えるための国策として誕生
DX認定制度が生まれた背景には、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」問題があります。これは、既存の老朽化したレガシーシステムが限界を迎え、IT人材不足も相まって日本企業の国際競争力が著しく低下するという危機的な予測です。
この問題を克服するため、経済産業省は企業経営者がDX推進に必要な事項を示した「デジタルガバナンス・コード」を策定しました。2020年の初版公表後、2022年には「デジタルガバナンス・コード2.0」へと改定され、2024年6月に見直しの検討を開始し、同年9月19日に「デジタルガバナンス・コード3.0」を策定・公表しました。
DX認定制度は、このコードに対応した準備ができている企業を認定することで、企業が自社のDX戦略を策定・公表し、組織体制を整える動機付けとなることを狙いとしています。単なる認定制度ではなく、日本企業全体のデジタル競争力向上を図る国家戦略の一環として位置づけられているのです。
個人事業主でも申請できる間口の広さ
DX認定制度の大きな特徴は、企業規模や業種、法人形態を問わず、あらゆる事業者が対象となることです。大企業はもちろん、中堅・中小企業、さらには個人事業主、公益法人、医療法人、NPO法人まで申請可能です。
実際に従業員数5名程度の小規模事業者や、創業間もないスタートアップ企業の認定例も多数あります。地方の小さな会計事務所が認定を取得し、補助金採択率の向上や新規顧客獲得につなげた事例も報告されています。
申請費用は完全無料で、オンラインでいつでも申請できる仕組みになっています。審査や問い合わせ対応は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が担当し、最終的な認定決定を経済産業省が行います。このように、どんな規模の事業者でも平等にチャンスがある制度設計となっているのが特徴です。
認定を受けるための7つの要件|ハードルは意外と高くない
DX認定を取得するには、経済産業省令で定められた7つの要件を満たす必要があります。一見すると難しそうに見えますが、実際は「DXを実施している」ことではなく「DXに向けた準備ができている」ことが要件となっているため、現時点でデジタル化が進んでいない企業でも十分に取得可能です。
要件1:経営ビジョン・DXビジョンの策定と公表
認定要件の最初のステップは、取締役会などの意思決定機関で承認された企業経営上のビジョンおよびDXのビジョンを策定し、対外的に公表することです。
これは単に内部で計画を持っているだけでなく、社外にも明確に示す必要があります。公表媒体はホームページやプレスリリース、統合報告書など形式は問われませんが、誰でもアクセスできる形で公開することが重要です。中小企業の場合、経営者自身がビジョンを定めて発信することでこの要件を満たすことができます。
要件2:経営戦略・DX戦略の策定と公表
ビジョンと同様に、企業経営戦略およびDX戦略も意思決定機関の決定に基づいて策定し、公表する必要があります。
戦略には、ビジョン実現のための具体的な道筋を示すことが求められます。例えば「顧客接点のデジタル化」「業務プロセスの自動化」「データ活用による新サービス創出」など、自社のDX推進の方向性を明確にします。これも社外から確認可能な形で公開することが必須となっています。
要件3:成果指標(KPI)の設定と公表
DX戦略の達成状況を評価するための指標(KPI)や目標値を定め、公表することも必要です。
KPIは定量的で測定可能なものである必要があります。例えば「3年以内に業務効率を40%向上」「顧客対応時間の20%削減」「デジタルチャネル経由の売上比率を50%に」といった具体的な数値目標を設定します。これにより、DX推進の進捗を客観的に評価できる仕組みを整えます。
要件4:DX推進責任者による情報発信
DX戦略推進の責任者(実務執行総括責任者)を明確にし、その責任者がDX推進に必要な情報発信を社内外に行うことが求められます。
大企業ではCDOやCIOが該当しますが、中小企業では経営者自身が責任者となるケースも多くあります。責任者は、DXの取り組み状況や成果について定期的に発信し、ステークホルダーとのコミュニケーションを図る役割を担います。
要件5:情報システムの課題把握
推進責任者は、自社で利用する情報システム上の課題をしっかり把握している必要があります。
老朽化した基幹系システムの存在、データのサイロ化、システム間連携の問題点などを認識し、解決に向けた計画を立てていることが重要です。この課題把握の方法として、IPAが提供する「DX推進指標」による自己診断を選択することができますが、独自の指標や分析手法を用いることも可能です。DX推進指標を使う場合は診断結果の提出が必要ですが、別の方法を選ぶ場合はその説明を申請書に記載すれば要件を満たします。
要件6:サイバーセキュリティ対策の実施
自社の情報システムやデータに対する適切なサイバーセキュリティ対策を策定・実施していることを示す必要があります。
ただし、高度なセキュリティシステムの導入が必須というわけではありません。企業規模に応じた適切な対策、例えばアクセス管理、定期的なバックアップ、セキュリティ教育の実施などがあれば要件を満たします。重要なのは、リスクを認識し対策を講じている姿勢です。
要件7:法令遵守(コンプライアンス)
最後の要件は、DX推進に関連して重大な法令違反がないことです。
これは最低限のコンプライアンス要件であり、健全な企業経営を行っていれば特に問題となることはありません。個人情報保護法、著作権法、不正競争防止法など、DXに関連する法令を遵守していることが前提となります。
これら7つの要件は「DXを大きく成功させていること」ではなく「DXに向けた計画・体制づくりができていること」を求めています。現時点でDXがあまり進んでいない企業でも、これからのビジョン・計画をしっかり策定し公開すれば申請資格は十分にあります。経済産業省も「DXを実際に推進している必要はないため比較的取り組みやすい」と説明しており、DXへの取組を始める企業が利用しやすいよう設計されています。
申請から認定までの実務フロー|標準60営業日で取得可能
DX認定の申請から取得まで、標準的なケースで60営業日(約3か月)程度かかります。申請受付は通年で行われており、締切などはないため、自社の準備が整い次第いつでも申請可能です。ここでは、実際の申請フローと注意すべきポイントを解説します。
申請書類の作成で押さえるべきポイント
申請にあたっては、まずIPAが提供する「DX認定制度 申請要項(ガイダンス)」や申請マニュアル、FAQを確認することから始めます。これらの資料はIPAの公式サイトから無料でダウンロードできます。
必要書類は主に、認定申請書(Word形式)と申請チェックシート(Excel形式)です。認定申請書では、設問(1)~(6)に沿って自社のDX推進状況を記述します。各設問には400~800字程度の記載欄があり、要件を満たす取り組みを具体的に説明します。
特に重要なのは、経営陣が承認したビジョンや戦略の内容と、それらを公開しているURLを明記することです。設問(5)の課題把握については、IPAの「DX推進指標 自己診断サイト」を利用する方法、Excelフォーマットに記入する方法、または独自の分析資料を提出する方法から選択できます。DX推進指標を使う場合は診断結果の提出が必要ですが、独自の方法で課題を把握している場合はその説明を申請書に記載すれば問題ありません。
審査でつまずきやすい箇所と対策
IPAによる審査では、形式面のチェック後、内容面の審査に移ります。審査期間は標準で60営業日(約3か月)が目安となっています。ただし申請件数や内容によって前後する場合があります。
よくある不合格ケースは、記載不足や要件漏れです。「経営陣承認を得たと明記していない」「公表URLが記載されていない、または内容が不足」「KPIが定量的でない」「情報システム課題が書かれていない」などが主な理由です。
これらを避けるため、申請前にチェックシートを活用して漏れがないか確認することが重要です。IPAは「よくある不備集」も公開しているので、事前に目を通しておくことをお勧めします。審査中にIPAから追加質問や修正依頼が来た場合は、指示に従い期限までに対応すれば、認定のチャンスは十分にあります。
2025年8月から始まるオンライン申請への移行
現在の申請方法は、Word/Excel様式をダウンロードして記入し、アップロードする方式ですが、2025年8月27日からは全面的にウェブフォーム入力型へ変更される予定です。
新方式では、DX推進ポータルの専用フォームにブラウザ上で直接入力し、そのまま送信する形になります。これにより様式のバージョン不整合やファイル不備を減らし、利便性と審査効率の向上が図られます。
申請にはgBizIDプライムという政府共通認証システムのアカウントが必要です。取得には代表者印等を用いた登録(郵送)が必要で、取得まで数日から2週間程度かかるため、早めの準備が重要です。既に補助金申請等でgBizIDを持っている場合は、それを流用できます。
認定取得で得られる3つの大きなメリット
DX認定を取得すると、企業には金融支援、人材育成支援、ブランド力向上という3つの大きなメリットがもたらされます。特に中小企業にとっては、DX推進の資金や人材不足という課題を解決する強力な支援となります。
低利融資と信用保証枠の拡大で資金調達が有利に
認定中小企業は、日本政策金融公庫の低利融資制度を利用できます。情報システム投資等に必要な資金に対し、基準利率よりも低い特別利率での融資を受けられます。
現在、基準金利1.75%に対し特別利率(Ⅱ)が1.10%と、約4割引きの金利優遇となっています。例えば1億円借入なら年間65万円の利息軽減につながる計算です。金利は経済情勢により変動するため、最新の情報は日本政策金融公庫のIT活用促進資金のページで確認することをお勧めします。
さらに、中小企業信用保険法の特例により、民間金融機関からの融資時に信用保証協会の保証枠が別枠で追加される措置も受けられます。これにより、情報システム関連の設備資金調達で信用保証枠の拡大や追加保証が得られ、融資を受けやすくなります。実際に地方の製造業が認定後すぐに地方銀行から低利融資を受けて基幹システムを刷新した事例も報告されています。
最大75%の助成金で人材育成コストを大幅削減
認定企業は厚生労働省の人材開発支援助成金(人への投資促進コース)において、「高度デジタル人材訓練」の対象事業主要件を満たします。
これにより、DX人材育成のため社員が研修を受講する際、研修費用の最大75%が助成されます。また、2025年度改正により、一部メニューの賃金助成上限が1時間あたり1,000円(中小企業・上限)に引き上げられました。対象コースや詳細な条件については、厚生労働省の最新資料で確認することが重要です。
DX推進には人材教育が欠かせませんが、中小企業では教育予算の確保が大きな課題です。認定を取得していればこうした助成を活用でき、社内DX人材の育成を加速できます。例えば100万円の研修費用が実質25万円の負担で済むことになり、人材投資のハードルが大幅に下がります。
企業ブランド力向上と採用競争力の強化
DX認定事業者として公式に認められることで、企業の対外的な信頼性が大きく向上します。IPAの認定事業者一覧に社名が掲載され、認定ロゴマークを自由に使用できるようになります。ただし、ロゴマークの使用には規約があり、変形不可、第三者商品パッケージでの使用不可など、適切な使用方法を守る必要があります。
特に人材採用面での効果は大きく、デジタルネイティブ世代の若手人材に「未来志向で魅力的な職場」という印象を与えることができます。実際に認定取得後、「DX認定の取得を機に採用募集で応募が増えた」「社内のIT人材が誇りを持った」という声が多く聞かれます。
また、まだDX認定企業が多くない地域では、「○○市で△△業として初のDX認定取得」といった形でプレスリリースを出すことで、地域メディアに取り上げられる可能性も高く、知名度向上につながります。
申請前に知っておきたい実務上の注意点
DX認定制度は比較的取り組みやすい制度ですが、申請前に理解しておくべき重要なポイントがいくつかあります。よくある誤解を解き、スムーズな認定取得につなげるための実務上の注意点を解説します。
「うちはまだDXなんて…」という企業ほど取るべき
多くの企業が「自社はまだDXが進んでいないから認定は無理」と考えがちですが、これは大きな誤解です。DX認定制度は、DXの実現度を問うものではありません。
重要なのは「DXに取り組む準備ができているか」という点です。現時点で業務が紙中心でアナログでも、これからDXに挑戦する意思と計画があれば認定される可能性は十分にあります。
むしろ、DXをこれから始める企業こそ、認定取得のプロセスを通じて自社の現状を整理し、明確な方向性を定めることができます。申請準備で経営ビジョンや戦略を改めて言語化することで、社内の意識統一も図れます。実際に「DX認定取得が社内改革のきっかけになった」という中小企業の声も多く聞かれます。
認定後の義務は?2年ごとの更新を忘れずに
認定の有効期間は2年間と定められており、認定日から起算して2年後の日付まで有効です。認定を維持するには、有効期限の60日前までに更新申請を行う必要があります。
更新申請は基本的に新規申請時とほぼ同じ内容の申請書を提出しますが、2年の間に自社の状況や目標が変わっていれば、その差分を修正します。制度や基準自体が見直されている場合もあるため、最新情報を確認しながら更新書類を作成することが重要です。
更新を怠ると認定は失効し、ロゴマークも使用できなくなります。ただし、認定取得後に特別な報告義務などはなく、通常の経営活動において追加の負担はありません。
不合格になるケースと再チャレンジの方法
審査で不合格となる主な理由は、形式要件の不備です。記載漏れや要件を満たしていない箇所があると指摘されますが、再チャレンジは可能です。
不合格の場合、IPAに問い合わせれば具体的な不備内容について教えてもらえる場合があります。指摘事項を改善した上で再申請すれば、認定を取得できる可能性は高まります。
DXそのものの優劣ではなく、形式要件を満たしているかが重視されるため、基本に忠実に記載することが合格への近道です。IPAは審査で疑問点があれば追加質問をしてくれるので、それに真摯に答えれば改善のチャンスがあります。
今が申請のチャンス!無料で得られる経営資源を最大限活用する
DX認定制度は、申請・維持費用が完全無料でありながら、金融支援、人材育成支援、企業価値向上という大きなメリットを得られる貴重な制度です。認定企業数は年々増加傾向にあり、特に中小企業での取得が急増しています。
制度改正により2024年9月19日に策定・公表されたデジタルガバナンス・コード3.0に基づく新基準が適用され、より実践的なDX推進が求められるようになりました。なお、以前存在した「DX投資促進税制」は2025年3月31日に廃止されましたが、現在も低利融資や助成金など、多様な支援策が用意されています。
認定取得後は専用のロゴマークを使用できますが、使用規約を遵守する必要があります(変形不可、不適切利用禁止等)。要件のハードルは決して高くなく、これからDXに取り組む企業でも十分に取得可能です。
認定取得は単なるステータスではなく、企業変革を加速させる実効的なツールとなります。2025年8月27日からはウェブフォーム入力による申請に全面移行される予定ですので、準備が整い次第、早めの申請をお勧めします。
解析人材育成
収集
CC-BizMate
勤怠管理クラウドサービスCC-BizMateは出退勤管理・勤怠管理・労務管理・工数管理・プロジェクト管理・在宅勤務・テレワーク勤務など「人事総務部門に寄り添う」サービスです!
CC-Smart
CC-Smartは、カラ予約の防止、議事録の録音、きめ細やかな通知機能など「会議のムダ」 「会議室のムダ」を省くことで生産性向上をサポートする会議予約システムです。
WebNESTEE STAMP
WebNESTEE STAMPは、書式にこだわらない出社せずにハンコ付き書類が作れるサービスです。事前に書式を準備する必要がなく、Excel、PDF、画像データを指定経路に回覧し、承認ができます。手続きや承認に時間や余計な手間をかけず、本来の仕事に集中できます。
groWiz
MS PowerPlatformサービスを用いたgroWizスタートアップ、アイデアサポート、オーダーメイド、テクニカルサポート等、ニーズに合わせたご提案をいたします。
OCVS構築支援サービス
クラウド環境向けに大幅な設計変更をすることなくクラウドリフトを実現し、Oracle Cloud Infrastructure上でこれまでと同じ操作方法のまま VMware 製品のツールを利用することができます。オンプレミスで運用しているVMwareの仮想サーバーをそのままOracle Cloud環境へ移行することも可能です。
活用・分析
CC-Dash AI
CC-Dashは、AI技術を活用したコンサルティングサービスとPoCサービスをご提供しています。
お客様のビジネス課題を解決するために、専門の技術チームがヒアリングからPoCまでの一連のプロセスをサポートいたします。
小売業向け CC-Dash AI
数多くのデータに数理的な処理を用いることで、将来の需要量、在庫量の予測が可能です。
小売業にAIを導入することにより、労働者不足問題の解消、属人化の防止、適正な在庫管理などに役立てられます。
Data Knowledge
Data Knowledgeは、30年に渡り使用されている国産のBIツールです。多彩な分析レポートで「経営の見える化」を促進し、分析ノウハウ共有機能で全社の分析レベルをアップ。データ・リテラシーの向上につながります。
BIスターターパック
by Tableau / by Oracle Analytics Cloud
Tableau は、クラウドベースの分析プラットフォームです。誰とでもデータからの発見を共有することができます。同僚やお客様を Tableau Cloud に招待し、インタラクティブなビジュアライゼーションと正確なデータを共有すれば、潜んでいるチャンスを探し出すこともできます。
ADB移行支援サービス
Oracle Autonomous Database(ADB)とはオラクル社の提供している高性能かつ運用負荷を限りなく軽減する自律型のデータベース・クラウド・サービスです。移行をすることで、利用時間に応じた課金体系で優れたコスト・パフォーマンスを実現します。
保守
CC-Dashの保守サービス
BI導入後、ツールを最大限に活用することをサポートします。約25年の実績で安心と信頼の“保守サービス”。
お客様のビジネス状況に応じたQA対応~システム運用まで幅広くトータルサポートを提供し、社内のエンジニアの稼働時間を年間330時間削減!
BIサポート定額オプションサービス
せっかくBIツールを導入してもうまく活用できない。そんな方のためにユーザー利用状況分析レポート、システムヘルスチェックレポートなどを通して、安定したシステム活用を目指すサービスです