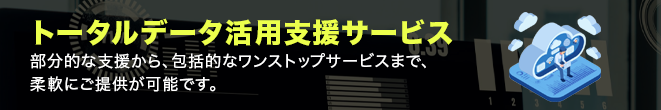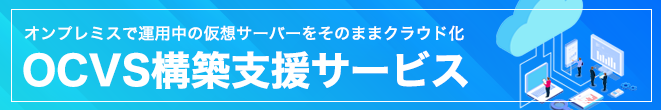【初心者向け】OCIサービスとは?特徴・メリット・料金をわかりやすく解説

【初心者向け】OCIサービスとは?特徴・メリット・料金をわかりやすく解説
企業のIT基盤をクラウドへ移行する動きが加速する中、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)が注目を集めています。OCIは、データベース分野で圧倒的な実績を持つオラクル社が提供するクラウドサービスです。AWSやAzureと比べて後発でありながら、エンタープライズ向けに特化した設計と優れたコストパフォーマンスで急成長を遂げています。本記事では、OCIサービスの基本から特徴、メリット、料金体系まで、初心者にも分かりやすく解説していきます。
目次
OCIサービスとは?Oracle Cloudの基本を理解する
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、オラクル社が提供する包括的なクラウドサービス基盤です。企業の基幹システムを支えるインフラからプラットフォーム、アプリケーションまで、150以上のサービスを統合的に提供しています。単なるクラウドサービスではなく、長年の企業向けソフトウェア開発で培った技術とノウハウを結集した、次世代のエンタープライズクラウドと位置づけられています。
Oracle Cloud Infrastructureが提供する統合クラウド基盤
OCIは、IaaS(Infrastructure as a Service)とPaaS(Platform as a Service)を一体化した統合基盤として設計されています。従来のクラウドサービスでは、インフラ層とプラットフォーム層が分離していることが多く、それぞれ個別に管理する必要がありました。
しかしOCIでは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングといった基本的なインフラ機能から、データベース、AI、分析ツールなどの高度なプラットフォーム機能まで、すべてが同一のアーキテクチャ上で動作します。この統合設計により、異なるサービス間の連携がスムーズになり、システム全体のパフォーマンスが向上します。
さらに重要な点は、オンプレミス環境で動作していたOracle製品群と同じ技術基盤を採用していることです。これにより、既存のシステムやアプリケーションをほぼそのままクラウドへ移行できる環境を実現しています。企業にとっては、これまでの投資や運用ノウハウを無駄にすることなく、クラウドの恩恵を受けられる理想的な選択肢となっています。
後発ながら急成長する世界50拠点のグローバル展開
OCIは2016年にサービスを開始した比較的新しいクラウドサービスですが、その成長スピードは目覚ましいものがあります。2025年現在、世界26か国に51のパブリッククラウド・リージョンを展開しており、この拡大ペースは主要クラウドベンダーの中でもトップクラスです。
後発であることを逆手に取り、既存クラウドサービスの課題を分析し、それらを解決する「第2世代クラウド」として設計されました。セキュリティやパフォーマンスの問題を根本から見直し、ゼロから構築することで、より安全で高速なクラウド基盤を実現しています。
日本国内では東京と大阪にリージョンを設置しており、国内企業のデータ主権要件にも対応可能です。各リージョンは同一のサービスレベルと料金体系で提供されているため、グローバル展開する企業にとっても管理しやすい環境となっています。金融業界や製造業など、ミッションクリティカルなシステムを運用する大手企業の採用も増えており、エンタープライズ市場での存在感を着実に高めています。
オンプレミスとクラウドを融合する次世代アーキテクチャ
OCIの最大の特徴の一つが、オンプレミスとクラウドの境界を意識させない独自のアーキテクチャです。多くの企業がすべてのシステムを一度にクラウド化することは現実的ではないため、段階的な移行や、一部システムをオンプレミスに残すハイブリッド構成が求められています。
OCIはこのニーズに応えるため、「Oracle Exadata Cloud@Customer」や「OCI Dedicated Region」といった革新的なソリューションを提供しています。これらのサービスでは、OCIのクラウドサービスを顧客のデータセンター内で利用することが可能です。
特にOCI Dedicated Regionは、OCIが提供する100以上のサービスすべてを顧客のデータセンター内で利用できる画期的な仕組みです。パブリッククラウドと同等の機能を、自社のセキュリティポリシーや規制要件に準拠した環境で運用できます。
また、マイクロソフトとの戦略的提携により、OCIとAzureを直接接続する高速インターコネクトも実現しています。これにより、両クラウド間でのデータ移動やアプリケーション連携が低遅延で可能となり、真のマルチクラウド環境を構築できます。
OCIの3つの特徴:エンタープライズクラウドの強み
OCIがエンタープライズ市場で選ばれる理由は、その独自の特徴にあります。Oracle製品との親和性、圧倒的な処理性能、そして政府認証レベルのセキュリティという3つの強みが、企業の厳しい要求に応えています。これらの特徴により、従来クラウド化が困難とされていた基幹システムの移行も現実的な選択肢となっています。
Oracle製品との完全な互換性と移行の容易さ
OCIを選択する最大のメリットは、既存のOracle製品との完全な互換性です。世界中の多くの企業が基幹システムでOracle Databaseを利用していますが、これらをクラウド化する際、他社クラウドでは様々な制約や追加コストが発生することがあります。
OCIであれば、オンプレミスで動作しているOracle Databaseをそのまま移行できます。データ形式の変換やSQL文の修正といった手間のかかる作業が不要で、移行リスクを最小限に抑えられます。
さらに、既存のOracleライセンスをOCIに持ち込むBYOL(Bring Your Own License)プログラムも利用可能です。他社クラウドでは同等の性能を得るために2倍以上のライセンスが必要になることもありますが、OCIならオンプレミスと同じライセンス数で運用できます。
運用面でも、これまで使用していた管理ツールやモニタリングツールをそのまま利用できるため、運用担当者の再教育コストも抑えられます。Oracle Enterprise ManagerやSQL Developerといった馴染みのあるツールで、クラウド環境も管理できる点は大きな安心材料となっています。
高性能インフラによる圧倒的な処理能力
OCIは、エンタープライズワークロードに求められる高い性能要件を満たすために、独自の高性能インフラを採用しています。仮想マシンだけでなく、ベアメタルサーバーも提供しており、最大192コアCPU、2.3TBメモリ、1PBストレージという大規模リソースを単一インスタンスで利用可能です。
性能面での革新的な取り組みとして、「オフボックス仮想化」技術があります。これは、ネットワークやストレージの処理を専用ハードウェアで行い、ホストサーバーのCPUリソースをアプリケーション処理に集中させる仕組みです。
この設計により、仮想化によるオーバーヘッドを最小限に抑え、他のユーザーの負荷に影響されない安定した性能を実現しています。ノンブロッキングネットワークの採用により、大規模環境でも低遅延で安定した通信が可能です。
Oracle DatabaseのReal Application Clusters(RAC)機能もOCI上でフル活用でき、数百から数千OCPUまでスケールアウトできます。金融機関の大量トランザクション処理や、製造業の大規模ERPシステムなど、これまでクラウド化が困難だった高負荷システムも、OCIなら安心して移行できる性能を備えています。
政府認証レベルの高度なセキュリティ基盤
OCIは設計段階から「Security by Design」の理念に基づいて構築されており、エンタープライズ利用に必要な高度なセキュリティを実現しています。2021年6月には、日本政府のクラウドセキュリティ評価制度「ISMAP」に登録され、政府機関での利用も可能な信頼性が公式に認められました。
セキュリティアーキテクチャの特徴として、ハイパーバイザーとネットワーク仮想化機能を物理的に分離し、専用ハードウェアで実装している点が挙げられます。これにより、仮想化レイヤーでのセキュリティリスクを大幅に低減しています。
Oracle Cloud Guardによるセキュリティ設定の自動検知、Security Zonesによるポリシーの強制適用、Autonomous Databaseによる自動パッチ適用など、セキュリティ運用を自動化する機能も標準で提供されています。
これらの機能は追加料金なしで利用でき、セキュリティ対策がクラウドサービスに組み込まれている点も特徴です。国際的な各種認証(ISO/IEC 27001、27017、27018)や、日本のFISC安全対策基準にも準拠しており、金融業界や医療分野など、高いセキュリティが求められる業界でも安心して利用できる基盤となっています。
企業が得られる4つのメリット:コストから性能まで
OCIを採用することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。コスト削減、既存資産の有効活用、高い信頼性、そして柔軟な構成という4つの観点から、OCIがもたらす実質的な価値を見ていきましょう。これらのメリットは、単なる理論上の話ではなく、実際の導入企業が体験している実績に基づいています。
他社クラウドの半額を実現する料金
OCIの最も魅力的なメリットの一つが、圧倒的なコストパフォーマンスです。実際の比較データによると、同等の構成でシステムを構築した場合、OCIの年間コストはAWSの約48%、Azureの約72%という結果が報告されています。
ネットワーク費用においても、OCIは大きなアドバンテージを持っています。データ転送料が月10TBまで無料という破格の設定で、AWSの月1GB無料枠と比較すると、その差は歴然です。
10TBを超えた分についても、OCIの転送料単価は他社の半額以下に設定されており、データ集約型のシステムでも安心して運用できます。Oracle FastConnectを利用したオンプレミスとの接続では、データ転送料が完全に無料となり、ポート料金のみで利用可能です。
既存Oracle資産を無駄にしないライセンス活用
多くの企業が長年にわたってOracle製品に投資してきた資産を、OCIなら最大限に活用できます。BYOL(Bring Your Own License)プログラムにより、既存のOracleライセンスをOCI上で使用でき、新たなライセンス購入コストを削減できます。
他社クラウドでOracle Databaseを運用する場合、クラウド環境特有の制約により、オンプレミスの2倍以上のライセンスが必要になるケースがあります。しかしOCIでは、オンプレミスと同じ条件でライセンスを使用できるため、追加コストが発生しません。
移行作業においても、Oracle Database間の移行であれば、スキーマの修正やSQL文の変更がほぼ不要です。異種データベースへの移行で発生する複雑な作業やリスクを回避でき、移行プロジェクトの期間短縮とコスト削減を実現できます。
運用面でも、Oracle Enterprise ManagerやSQL Developerといった既存の管理ツールをそのまま使用できるため、運用チームの学習コストを最小限に抑えられます。これらの要素により、TCO(総所有コスト)の観点から見ても、Oracle製品を利用している企業にとってOCIは最適な選択肢となっています。
ISMAP適合による官公庁レベルの信頼性
OCIが2021年6月にISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)に登録されたことは、企業にとって大きな安心材料となっています。ISMAPは、日本政府が定める厳格なセキュリティ基準であり、この認証を取得したクラウドサービスは、政府機関での利用が認められます。
この認証は、単に技術的なセキュリティレベルが高いことを示すだけでなく、運用体制やガバナンス、コンプライアンス面でも高い水準を満たしていることを意味します。金融業界や医療分野など、規制の厳しい業界でクラウド導入を検討する際の重要な判断材料となっています。
実際に、官公庁や地方自治体、大手金融機関でもOCIの採用が進んでおり、ミッションクリティカルなシステムの運用実績が蓄積されています。
企業の経営層や情報セキュリティ責任者に対しても、「政府が認めた安全なクラウド」という説明ができることで、社内外の承認を得やすくなるメリットもあります。顧客データや機密情報を扱うシステムのクラウド化において、このような公的な認証は非常に重要な要素となっています。
ハイブリッド・マルチクラウドへの柔軟な対応
現代の企業IT戦略において、単一のクラウドベンダーに依存しない柔軟性は重要な要素です。OCIは、この点でも優れた選択肢を提供しています。OCI Dedicated Regionサービスでは、OCIの100以上のサービスすべてを顧客のデータセンター内で利用可能で、パブリッククラウドの利便性とオンプレミスのセキュリティを両立できます。
特筆すべきは、マイクロソフトとの戦略的提携による Azure との連携です。OCIとAzure間は専用の高速インターコネクトで接続され、両クラウドのリソースを低遅延で相互利用できます。
2023年には「Oracle Database@Azure」サービスも開始され、Azureの管理画面からOracle Databaseをプロビジョニングできるようになりました。これにより、Azureユーザーも簡単にOracleの高性能データベースを利用できる環境が整いました。
このような柔軟な構成により、企業は最適なサービスを最適なクラウドから選択し、組み合わせて利用することが可能です。将来的なIT戦略の変更にも対応しやすく、ベンダーロックインのリスクを軽減できる点も、OCIを選択する大きなメリットとなっています。
OCIの料金はどれくらい?
OCIは、シンプルで予測可能な料金体系を採用しており、想定外のコストが発生しにくい設計となっています。従量課金と年間契約の2つのプランから選択でき、企業の利用パターンに応じた最適な選択が可能です。
使った分だけ支払う従量課金
OCIの基本的な料金プランである「Pay As You Go(PAYG)」は、使った分だけを月次で後払いする従量課金モデルです。初期費用や最低利用期間の縛りがなく、必要な時に必要なだけリソースを利用できる柔軟性が特徴です。
このプランは、短期的なプロジェクトや、将来の利用規模が予測しにくい場合に適しています。例えば、新しいアプリケーションの開発段階では小規模に始め、需要の増加に応じて段階的にリソースを拡張していくといった使い方が可能です。
リソースが不要になればすぐに停止でき、その時点でコストもゼロになるため、無駄な支出を避けられます。ただし、各サービスにはデフォルトの利用上限が設定されており、大規模な利用を予定している場合は、事前に上限緩和の申請が必要な場合があります。
これは、予期せぬ高額請求を防ぐための安全策でもあり、特に初めてクラウドを利用する企業にとっては安心できる仕組みとなっています。
出典:Oracle Cloud価格表ページ
他社よりも安い理由
OCIが他社クラウドよりも低価格を実現できる理由はいくつかあります。まず、全世界のリージョンで統一価格を採用している点が挙げられます。他社では地域により価格差がありますが、OCIは東京でも北米でも同じ料金体系です。
また、基本料金に標準サポートが含まれている点も重要です。他社では別途サポート料金が必要な場合が多いですが、OCIでは追加費用なしで技術支援を受けられます。
ネットワークコストの面でも大きな優位性があります。月10TBまでのデータ転送が無料という設定は、他社の無料枠と比較して桁違いの規模です。さらに、FastConnectを利用したオンプレミス接続では、データ転送料が完全無料となります。
サービス構成のシンプルさも、コスト削減に寄与しています。OCIのサービス数は約100程度と他社より少ないですが、これは重複を避け、必要十分な機能に絞り込んだ結果です。監視やセキュリティ機能も標準で含まれており、隠れたコストが発生しにくい透明性の高い料金体系となっています。
無料で始められるOCI
OCIを本格導入する前に、無料で試せる充実した制度が用意されています。30日間の無料トライアルと、期限なしで利用できるAlways Freeサービスにより、リスクなくOCIの性能や使い勝手を検証できます。これらの無料枠を活用することで、導入前の不安を解消し、確実な移行計画を立てることが可能です。
30日間300ドル分の無料トライアル
OCIの無料トライアルでは、アカウント作成時に300米ドル分のクレジットが付与され、最大30日間にわたってほぼすべてのOCIサービスを試すことができます。この期間内であれば、高性能なGPUインスタンスや大容量ストレージなど、通常は高額なリソースも自由に利用できます。
登録時にクレジットカード情報の入力が必要ですが、これは本人確認のためであり、30日間の無料期間中に自動的に課金されることはありません。ユーザーが明示的に有償プランへアップグレードしない限り、料金は発生しない仕組みです。
300ドルという金額は、小規模なシステムであれば30日間フルに稼働させても使い切れないほど充実しています。例えば、標準的な仮想マシン1台であれば月数十ドル程度で運用可能なため、複数のサービスを組み合わせた本格的な検証環境を構築できます。
無料トライアル期間中に作成したリソースは、有償プランへアップグレードすればそのまま継続利用可能です。検証環境をそのまま本番環境として活用できるため、移行作業の手間も削減できます。
出典:Oracle Cloud Free Tierページ
ずっと無料で使えるサービス
OCIの「Always Free」サービスは、期間制限なく永続的に無料で利用できる画期的な制度です。無料トライアル終了後も、OCIアカウントを持っていれば継続して利用可能で、小規模なシステムであれば完全無料で運用を続けることができます。
Always Freeの対象サービスには、仮想マシン2台(各1OCPU、1GBメモリ)、ブロックストレージ200GB、オブジェクトストレージ20GB、さらにはAutonomous Database 2インスタンス(各20GB)が含まれています。
これらのリソースは、個人の学習用途や小規模な開発環境には十分な規模です。特にAutonomous Databaseが無料で利用できる点は、Oracleの最新データベース技術を体験できる貴重な機会となっています。
他社クラウドの無料枠が12か月限定であることが多い中、OCIのAlways Freeは期限がないため、時間を気にせずじっくりと学習や検証を行えます。監視、ログ管理、通知サービスなどの運用系機能も無料枠に含まれており、実際の運用を想定した検証が可能です。
無料期間を活用した導入前の検証方法
無料トライアルとAlways Freeを組み合わせることで、効果的な導入前検証を実施できます。まず30日間の無料トライアルで、実際の本番環境に近い構成でシステムを構築し、性能測定や互換性の確認を行います。
検証すべきポイントとしては、既存システムとの接続性、レスポンスタイムやスループットの測定、セキュリティ設定の動作確認などが挙げられます。Oracle Databaseを使用している場合は、移行後の動作確認やパフォーマンスチューニングも重要です。
無料トライアル終了後は、Always Freeリソースを活用して長期的な検証を継続できます。小規模な検証環境を維持し、定期的なアップデートの確認や、新機能のテストなどを行うことが可能です。
社内教育にも活用でき、エンジニアにOCIアカウントを配布して実際に操作してもらうことで、スキルの習得を促進できます。Oracleが提供する無料のオンライントレーニング教材と組み合わせることで、効果的な人材育成プログラムを構築できます。
まとめ:OCIで実現する次世代IT基盤への転換
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、エンタープライズ向けに特化した設計と、優れたコストパフォーマンスを両立させた次世代クラウドサービスです。後発ながら急速に成長し、世界51拠点でサービスを展開するまでに至りました。Oracle製品との完全な互換性、圧倒的な処理性能、政府認証レベルのセキュリティという3つの特徴により、これまでクラウド化が困難だった基幹システムの移行も現実的になっています。
コスト面では他社クラウドの約半額という圧倒的な優位性を持ち、既存のOracleライセンス資産も有効活用できます。ISMAP認証による信頼性と、ハイブリッド・マルチクラウドへの柔軟な対応力により、企業の多様なニーズに応えます。充実した無料トライアルとAlways Freeサービスにより、リスクなく導入検証を行える点も大きな魅力です。
デジタルトランスフォーメーションが求められる現代において、OCIは企業のIT基盤を次世代へと転換する強力な選択肢となるでしょう。特にOracle製品を利用している企業や、コスト最適化を重視する企業にとって、OCIは検討すべき有力なクラウドサービスです。まずは無料トライアルから始めて、その実力を体験してみることをお勧めします。
解析人材育成
収集
CC-BizMate
勤怠管理クラウドサービスCC-BizMateは出退勤管理・勤怠管理・労務管理・工数管理・プロジェクト管理・在宅勤務・テレワーク勤務など「人事総務部門に寄り添う」サービスです!
CC-Smart
CC-Smartは、カラ予約の防止、議事録の録音、きめ細やかな通知機能など「会議のムダ」 「会議室のムダ」を省くことで生産性向上をサポートする会議予約システムです。
WebNESTEE STAMP
WebNESTEE STAMPは、書式にこだわらない出社せずにハンコ付き書類が作れるサービスです。事前に書式を準備する必要がなく、Excel、PDF、画像データを指定経路に回覧し、承認ができます。手続きや承認に時間や余計な手間をかけず、本来の仕事に集中できます。
groWiz
MS PowerPlatformサービスを用いたgroWizスタートアップ、アイデアサポート、オーダーメイド、テクニカルサポート等、ニーズに合わせたご提案をいたします。
OCVS構築支援サービス
クラウド環境向けに大幅な設計変更をすることなくクラウドリフトを実現し、Oracle Cloud Infrastructure上でこれまでと同じ操作方法のまま VMware 製品のツールを利用することができます。オンプレミスで運用しているVMwareの仮想サーバーをそのままOracle Cloud環境へ移行することも可能です。
活用・分析
CC-Dash AI
CC-Dashは、AI技術を活用したコンサルティングサービスとPoCサービスをご提供しています。
お客様のビジネス課題を解決するために、専門の技術チームがヒアリングからPoCまでの一連のプロセスをサポートいたします。
小売業向け CC-Dash AI
数多くのデータに数理的な処理を用いることで、将来の需要量、在庫量の予測が可能です。
小売業にAIを導入することにより、労働者不足問題の解消、属人化の防止、適正な在庫管理などに役立てられます。
Data Knowledge
Data Knowledgeは、30年に渡り使用されている国産のBIツールです。多彩な分析レポートで「経営の見える化」を促進し、分析ノウハウ共有機能で全社の分析レベルをアップ。データ・リテラシーの向上につながります。
BIスターターパック
by Tableau / by Oracle Analytics Cloud
Tableau は、クラウドベースの分析プラットフォームです。誰とでもデータからの発見を共有することができます。同僚やお客様を Tableau Cloud に招待し、インタラクティブなビジュアライゼーションと正確なデータを共有すれば、潜んでいるチャンスを探し出すこともできます。
ADB移行支援サービス
Oracle Autonomous Database(ADB)とはオラクル社の提供している高性能かつ運用負荷を限りなく軽減する自律型のデータベース・クラウド・サービスです。移行をすることで、利用時間に応じた課金体系で優れたコスト・パフォーマンスを実現します。
保守
CC-Dashの保守サービス
BI導入後、ツールを最大限に活用することをサポートします。約25年の実績で安心と信頼の“保守サービス”。
お客様のビジネス状況に応じたQA対応~システム運用まで幅広くトータルサポートを提供し、社内のエンジニアの稼働時間を年間330時間削減!
BIサポート定額オプションサービス
せっかくBIツールを導入してもうまく活用できない。そんな方のためにユーザー利用状況分析レポート、システムヘルスチェックレポートなどを通して、安定したシステム活用を目指すサービスです